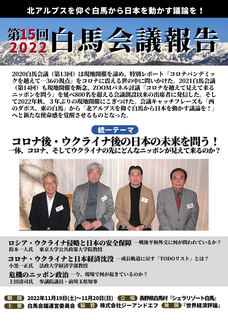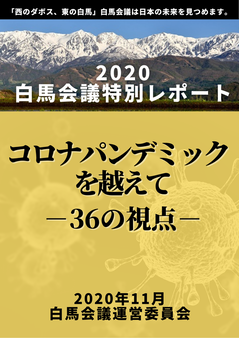2023 白馬会議(第16回)報告
どうする原発
—コモン・センスで問え!日本のエネルギー選択--
|
2011年3月11日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所事故は全ての日本人に脱原発への道を思いしらせたかに見えたが、私たちの議論は再び迷走し始めている。かつてトマス・ペインはアメリカ独立戦争の最中、歴史的著書『コモン・センス』を著わし、「イギリスからの独立」がアメリカ国民にとっての「コモン・センス」すなわち「自明の理」であると訴えた。それでは今、日本国民にとって「脱原発」は果たして「コモン・センス」と言えるのか?原発継続を巡る“二項対立”的論争を超え日本国民にとって真に「コモン・センス」に適うエネルギー選択とは何かを問いかけた。
| |||||||
日時:2023年11月18日(土) ~11月19日(日)
会場:白馬樅木ホテル https://www.mominokihotel.com/
主催:白馬会議運営委員会
後援:『世界経済評論』http://www.world-economic-review.jp/
協賛:株式会社 ジーアンドエフ https://www.gandf.co.jp/
会場:白馬樅木ホテル https://www.mominokihotel.com/
主催:白馬会議運営委員会
後援:『世界経済評論』http://www.world-economic-review.jp/
協賛:株式会社 ジーアンドエフ https://www.gandf.co.jp/
第1セッション
「大地震と原発事故―過去の教訓にどう立ち向かうか?」
―原発が大地震に見舞われた時の災害リスクにつき福島第一原発の教訓を踏まえながら、
地震列島に原発を立地する意味を考える。
By 立石雅昭氏 新潟大学理学部名誉教授
―原発が大地震に見舞われた時の災害リスクにつき福島第一原発の教訓を踏まえながら、
地震列島に原発を立地する意味を考える。
By 立石雅昭氏 新潟大学理学部名誉教授
第2セッション
「原発の正義とは?原発訴訟での司法の役割と可能性」
―専門技術主義と先例主義に傾斜してしまった原発差止め裁判の現場から、
本来守るべき司法の正義を問う。
By 樋口英明氏 福井地裁元裁判長
―専門技術主義と先例主義に傾斜してしまった原発差止め裁判の現場から、
本来守るべき司法の正義を問う。
By 樋口英明氏 福井地裁元裁判長
第3セッション
「やってはいけない原発ゼロ―人類文明と原子力技術」
―人類文明の未来を考えるとき、本当に原子力技術を諦めてしまっていいのか?
タブーと先入観を超え敢えて問う。
By 澤田哲生氏 エネルギーサイエンティスト
元東京工業大学ゼロカーボンエネルギー研究所
―人類文明の未来を考えるとき、本当に原子力技術を諦めてしまっていいのか?
タブーと先入観を超え敢えて問う。
By 澤田哲生氏 エネルギーサイエンティスト
元東京工業大学ゼロカーボンエネルギー研究所
第4セッション
「原発はグリーンか?―目指すべき脱炭素化戦略とは」
―原発は果たして脱炭素化を推進する有力な政策選択の1つとなり得るのか?
原子力に頼らない社会の可能性を模索する。
By 松久保肇氏 原子力資料情報室事務局長
経産省原子力小委員会委員
―原発は果たして脱炭素化を推進する有力な政策選択の1つとなり得るのか?
原子力に頼らない社会の可能性を模索する。
By 松久保肇氏 原子力資料情報室事務局長
経産省原子力小委員会委員
2022 白馬会議(第15回)報告
さよならダボスー白馬から日本を動かす議論を
~白馬会議はSEASON2へ~
コロナで足踏みを余儀なくされた白馬会議は3年ぶりに現地開催に漕ぎつけた。何人集まって来るのか?正直、一抹の不安があったが、3名のゲスト講師を含め40名の参加者が結集した。これで行ける。報告書作成(2022年)、ZOOMシンポジウム(2021年)とコロナ渦を凌いで昨秋、北アルプスの麓に戻った15回目の白馬会議はその底力を証明した。
「西のダボス、東の白馬」と2008年の白馬会議発足以来、追いかけて来たダボス会議はどうか。1971年にスイスダボス村で創設された時はヨーロッパ人中心の集まりであった。それが1989年のベルリンの壁崩壊、冷戦終結をもって大化けした。東西南北、世界各国の首脳や国際機関の代表、企業経営者ら3000人を超える参加者の集う今のダボス会議にのし上がった。それから30余年が経過しコロナパンデミックに遭遇する中、2021年は中止。2022年はロシアのウクライナ侵略で5月に延期開催され、本年1月に通常開催に戻った。
しかし、ダボス会議は今、大きな曲がり角に立っている。先ずは今回の会議テーマ「分断された世界における協力」でベルリンの壁崩壊以後出現したグローバルダボスの時代が終わったことを認めた。G7首脳の内、出席したのはドイツのショルツ首相のみだった。オルガルヒ(ロシア新興財閥)やジャック・マーのような中国富裕経済人たちも会場から姿を消していた。参加者総数も3000人を下回った。
『文明の衝突』を著わした米政治学者ハンチントンは西欧を源流とする「ダボス文化」を共有できるのは世界人口の1%に過ぎず、人類は「多極的で多文明的な世界」に向かわざるを得ないと批判していた。ハンチントンは我が日本文明を世界八大文明のひとつに加えながらも、「一民族一国家で形成される特異な文明」と異端視していた。その日本からは結局、一部のダボスおたくを除きダボス会議人脈の中枢に入り込もうとする者はいなかった。
「堂々たるニッポン主義」―白馬会議は何処まで行っても日本人参加者中心の「FOR JAPAN」論議である。白馬に様々な舞台で活動する「志ある知的日本人」が毎年集まって来て、「世界における日本の針路」と「日本国民のコモンセンス」について意見をたたかわせる。この開き直りがダボス会議の黄昏を感じる今、私たちの覚悟、プライドそして使命感として輝き始めた気がする。「北アルプスを仰ぐ白馬から日本を動かす議論を!」―白馬会議SEASON2の始まりだ。
「西のダボス、東の白馬」と2008年の白馬会議発足以来、追いかけて来たダボス会議はどうか。1971年にスイスダボス村で創設された時はヨーロッパ人中心の集まりであった。それが1989年のベルリンの壁崩壊、冷戦終結をもって大化けした。東西南北、世界各国の首脳や国際機関の代表、企業経営者ら3000人を超える参加者の集う今のダボス会議にのし上がった。それから30余年が経過しコロナパンデミックに遭遇する中、2021年は中止。2022年はロシアのウクライナ侵略で5月に延期開催され、本年1月に通常開催に戻った。
しかし、ダボス会議は今、大きな曲がり角に立っている。先ずは今回の会議テーマ「分断された世界における協力」でベルリンの壁崩壊以後出現したグローバルダボスの時代が終わったことを認めた。G7首脳の内、出席したのはドイツのショルツ首相のみだった。オルガルヒ(ロシア新興財閥)やジャック・マーのような中国富裕経済人たちも会場から姿を消していた。参加者総数も3000人を下回った。
『文明の衝突』を著わした米政治学者ハンチントンは西欧を源流とする「ダボス文化」を共有できるのは世界人口の1%に過ぎず、人類は「多極的で多文明的な世界」に向かわざるを得ないと批判していた。ハンチントンは我が日本文明を世界八大文明のひとつに加えながらも、「一民族一国家で形成される特異な文明」と異端視していた。その日本からは結局、一部のダボスおたくを除きダボス会議人脈の中枢に入り込もうとする者はいなかった。
「堂々たるニッポン主義」―白馬会議は何処まで行っても日本人参加者中心の「FOR JAPAN」論議である。白馬に様々な舞台で活動する「志ある知的日本人」が毎年集まって来て、「世界における日本の針路」と「日本国民のコモンセンス」について意見をたたかわせる。この開き直りがダボス会議の黄昏を感じる今、私たちの覚悟、プライドそして使命感として輝き始めた気がする。「北アルプスを仰ぐ白馬から日本を動かす議論を!」―白馬会議SEASON2の始まりだ。
≪テーマ2022≫
コロナ後・ウクライナ後の日本の未来を問う!
一体、コロナ、そしてウクライナの先にどんなニッポンが見えて来るのか?
下記3つのセッションを軸にして熱論を展開した。
下記3つのセッションを軸にして熱論を展開した。
| |||||||
【2021年第14回白馬会議(ZOOM)報告】
コロナのため2020年に続き白馬会議の現地開催を2021年も諦めざるを得なかった。但し、この2年間、私達はコロナの前で只、足踏みをしていただけではない。様々な現場でコロナと格闘しながら、実はコロナを越えて見えて来る新たなニッポンを模索していたのではないか?そんな問題意識と期待の中で、過去12回の白馬会議に集った延べ800名の方々に呼びかけ、2021年はZOOMシンポジウムを開催、2022秋の白馬会議再開に向けた知力充実と心意気を喚起した。
開催日時:2021年11月28日(SUN) 14:00~16:30 (ZOOM)
テーマ:コロナを越えて見えて来るニッポンを問う!
―政治・経済・外交の視点からー
コロナを越えるニッポンにどんな未来が開けて来るのか?目先の楽観、悲観に振り回されずに、これから向かうべき日本の姿を政治、経済、外交それぞれの視点から注目すべき3人の論客を招いて徹底討議しました。
〈プロフィール〉
東京大学法学部卒業。東京都立大学法学部助教授を経て、東京大学大学院法学政治学研究科教授。専門は自治体行政学。著書に『コロナ対策禍の国と自治体』『行政学講義-日本官僚制を解剖する』『地方創生の正体』等。
東京大学法学部卒業。東京都立大学法学部助教授を経て、東京大学大学院法学政治学研究科教授。専門は自治体行政学。著書に『コロナ対策禍の国と自治体』『行政学講義-日本官僚制を解剖する』『地方創生の正体』等。
〈プロフィール〉
横浜国立大学経済学部卒業後、大和証券を経てドイツ証券入社し、調査部長兼チーフストラテジスト、副会長兼チーフ・インベストメント・アドバイザーを歴任。2009年武者リサーチ設立。著書は『アフターコロナ V字回復する世界経済』『史上最大の「メガ景気」がやってくる』『超金融緩和の時代』等。
横浜国立大学経済学部卒業後、大和証券を経てドイツ証券入社し、調査部長兼チーフストラテジスト、副会長兼チーフ・インベストメント・アドバイザーを歴任。2009年武者リサーチ設立。著書は『アフターコロナ V字回復する世界経済』『史上最大の「メガ景気」がやってくる』『超金融緩和の時代』等。
〈プロフィール〉
東北大学歯学部卒業。米国ニュースクール大学政治学修士課程修了。米戦略国際問題研究所(CSIS)上級研究員を経て2005年帰国、三井物産戦略研究所、東京財団から現職。著書は『2021年以後の世界秩序』 『2025年米中逆転』『「今のアメリカ」がわかる本』等。
東北大学歯学部卒業。米国ニュースクール大学政治学修士課程修了。米戦略国際問題研究所(CSIS)上級研究員を経て2005年帰国、三井物産戦略研究所、東京財団から現職。著書は『2021年以後の世界秩序』 『2025年米中逆転』『「今のアメリカ」がわかる本』等。
【2020 白馬会議特別レポ―ト】
コロナパンデミックを越えて
-36の視点-
コロナが本格化した20202年は白馬村での会議開催を断念。2008年に開催した第1回より白馬会議に集ってきた「知的個人」の中から「有志的論客」36名の皆さんに依頼し、コロナに立ち向かうショートメッセージを寄稿して頂いた。
|
※2020年特別レポートは以下よりダンロードできます。
| |||||||
【2019年第12回白馬会議討議報告】
令和の始まりはどことなく明るいムードが漂っていたが、新しい時代をどう切り拓くか明確なビジョンが示されているわけではない。12年目の白馬会議では「令和ニッポンの青写真を描け」と意気込んだが、青写真の下書きを持ち帰った実感はなかった。我々の眼前は依然と荒野である。
第1セッション
“第4の波”にどう立ち向かうか?―ブロックチェーン革命とサイバーセキュリティ
松田 学氏 (松田政策研究所代表)
第2セッション
21世紀前半の日本政府の進路
金井 利之氏 (東京大学大学院法学政治学研究科教授)
第3セッション
米中超大国間でどうバランスをとるか?―日本外交模索の先
川島 真氏 (東京大学大学院総合文化研究科教授)
第4セッション
若者はどう未来をつかもうとしているのか?-世代間キャップを越えて
西田 亮介氏 (東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授)
“第4の波”にどう立ち向かうか?―ブロックチェーン革命とサイバーセキュリティ
松田 学氏 (松田政策研究所代表)
第2セッション
21世紀前半の日本政府の進路
金井 利之氏 (東京大学大学院法学政治学研究科教授)
第3セッション
米中超大国間でどうバランスをとるか?―日本外交模索の先
川島 真氏 (東京大学大学院総合文化研究科教授)
第4セッション
若者はどう未来をつかもうとしているのか?-世代間キャップを越えて
西田 亮介氏 (東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授)
|
|
お問合せ:白馬会議運営委員会
〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘5-3-5-201 TEL: 080-3712-1951 EMAIL: i c h i @ g b 3 . s o - n e t . n e . j p